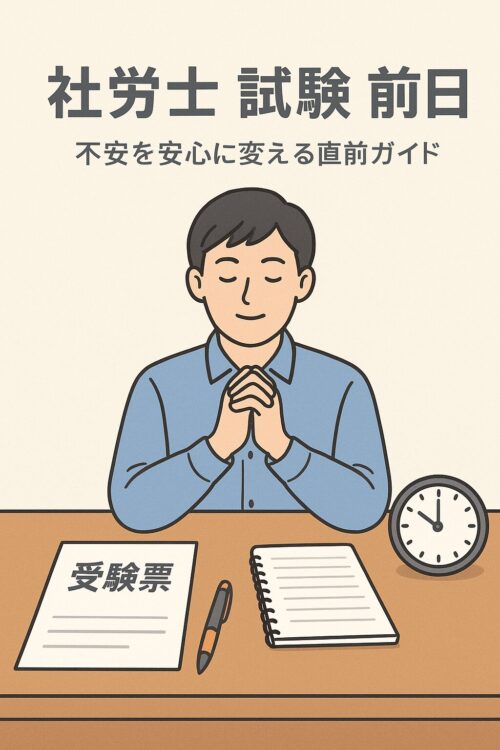はじめに
社労士模試の点数がボロボロ…それでも合格は可能です!
「社労士の模試でボロボロの点数だった…」「もう無理かもしれない」と落ち込んでいませんか?
安心してください。模試の結果が悪くても、社労士本試験に合格している人はたくさんいます。むしろ、模試で失敗したことをバネにして、合格を勝ち取った人の方が多いのです。
本記事では、「不模試D判定から合格レベルに乗るための具体的な学習プラン」「やってはいけないNG行動」などを実際の体験談とともに紹介します。
【失敗から学ぶ】模試の点数が悪かったときにやるべきこと
模試の結果を感情で終わらせない
模試で点数が悪いと、落ち込んで手が止まる人が多いですが、ここで大事なのは「分析」
点数はただの通過点です。合格との距離を測るための「データ」として捉えましょう。
また、模試は各予備校が、問題をひねって作成されていることもあり、模試の方が難しかったりしますので、落ち込む必要はありません。
間違えた問題を宝の山に変える。復習する時は難問にこだわらない
模試の問題こそ、弱点をあぶり出す最強のツールです。「なぜ間違えたのか」「どうすれば次に正解できるか」を分析しましょう
ここで、注意が必要なのは、間違えた問題をすべて時間をかけて復習しない
全受験生の正答率50%以上の問題を落とさないように復習しましょう
難問や、知らない問題、聞いたことのない選択肢の知識を増やすのではなく、基本的な知識を固めてい久野です
本番レベルの時間配分と緊張感を体得する
模試は試験本番と同じ時間配分・同じ緊張感で解くことが重要です。
特に択一式は時間との勝負。本番に向けて、模試のたびに「戦い方」を身につけていくことが合格への鍵です。
【模試で学ぶ】点数よりも大切な「気づき」
社労士試験は、知識の正確さに加え、「試験で力を出せるか」が問われます。
模試を通じて、
- 試験時間にどのように集中力を維持するか
- 自分が緊張するとどのようなミスをしやすいか
- 苦手な法令科目や選択式の対応法
などを把握し、本試験では「冷静な判断力」と「安定した得点力」を発揮できるようにしておきましょう。
【リカバリー法】模試ボロボロから立て直す勉強法
選択式の点数が低い場合
- テキスト読みの学習を増やす
- 目的条文を毎日確認
択一式で時間切れになる場合
- 1問 2分30秒で解く訓練
- 難問に力を入れず、取れる問題を落とさない訓練
【体験ベース】金沢先生のブログから学ぶD判定→合格の学習戦略
大原で人気の講師・金沢先生は、ご自身のブログでこう述べています。
「模試でD判定だった方が、最終的に本試験で合格しているケースは少なくありません。重要なのは、その後の取り組み方です」
これらを守ることで、合格レベルに着実に近づくことができます。
金沢先生の「逆転合格6ステップ学習プラン」
教材を「基本テキスト」と「択一式問題集」に絞る
教材をあれこれ増やすのではなく、大原の基本テキストと択一式問題集に徹底集中。
「教材迷子」になるより、同じ教材を繰り返すことが合格への近道です。
❝やる教材を増やすのではなく、深く掘り下げること❞(金沢先生ブログより)
問題を解いたら、必ずテキストを確認する
ただ解いて終わりにしない。**「なぜ間違えたのか?」「どこに書いてあったのか?」**を必ず確認。
特に初見問題で間違えた箇所は、知識の穴を埋める重要なヒントになります。
論点はテキストに書き込む
テキストは「読むもの」ではなく、「作り込むもの」。
- 正誤判断の根拠
- 自分の引っかかったポイント
- 自分の言葉での補足説明
などを、**余白にどんどん書き込むことで、世界に一つだけの“最強の参考書”**が完成します。
問題の出題箇所の“周辺知識”も確認する
出題された箇所だけでなく、その前後の条文や制度の流れも確認。
社労士試験では「出題された部分の周辺知識」が問われることが非常に多いため、ここは見落とせません。
1週間で2科目を目安に学習する
「1週2科目」のペースを守れば、約4週間で1周、8週間で2周目に入れます。
このサイクルで回せば、直前期に「忘れてしまった…」という状態を防げます。
ラスト1週間はテキストを通読して総復習
直前の1週間は、「問題演習ではなく、テキストの通読」を重視。
- 書き込み済みのテキストを使って知識を総ざらい
- 過去に間違えた箇所に付箋を貼り、そこだけ重点復習
- 通勤や空き時間に音声でテキスト要点を聞き流すのも有効
❝試験1週間前から新しいことをするのは逆効果。“仕上げる”意識で復習に集中を❞(金沢先生)
【やってはいけない】模試で失敗した人が取りがちなNG行動
❌ あきらめる
これが一番NG行動です。
D判定は決して絶望ではありません。 最後まで粘ることが合格への一番の近道です。
❌ 山あてをする
不得意科目に力をかけるのは良いですが、それでも全科目 網羅的に勉強しましょう
自己流で絞ったり、予備校の直前まとめ、法改正だけに絞ったりしてはいけません
❌ 選択対策ばかりに偏る
選択式も重要ですが、合否を分けるのは択一式の得点力。全体のバランスを意識しましょう。
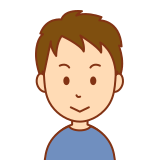
僕も 選択式に偏った学習をした年は、択一の得点が大幅に下がってしまいました。
❌新しい教材を追加する
この時期に新しい教材を追加するのは危険です。本試験まで消化不良になる可能性大
法改正、白書対策を購入するの仕方がないのですが、択一問題、選択問題 テキストなどは
新たに購入しないようにしましょう
【心構え】模試の点数に振り回されないメンタルの保ち方
合格者の多くも「本試験が一番点が良かった」
模試の成績が振るわなくても、本番で得点が伸びた合格者は多数います。
本番の伸びしろはここから
直前期の学習次第で、点数は大きく変わります。
SNSや他人と比較しすぎない
他人の点数ではなく、自分の改善に集中することが大切です。
【まとめ】模試がダメでも合格できる!失敗を力に変えよう
社労士試験は、知識だけでなく「試験戦略」と「粘り強さ」が問われる試験です。
模試がボロボロでも、大丈夫。
むしろ、その失敗をどう活かすかが合格の鍵になります。
✅ 社労士模試がボロボロでも合格できる理由:
- 本試験までの伸びしろがある
- 模試の失敗で「弱点」が明確になる
- 多くの合格者も模試では失敗していた
✅ 今からできること:
- 模試を冷静に分析し、苦手分野を把握する
- 時間配分や試験当日の流れを意識した演習を重ねる
【最後に】模試の失敗こそ、最高の教材
模試で失敗しても、社労士試験の合格は可能です。
「失敗=成長のきっかけ」です。
焦らず、腐らず、自分のペースで勉強を続けましょう。
あなたの努力は、必ず本試験で実を結びます。