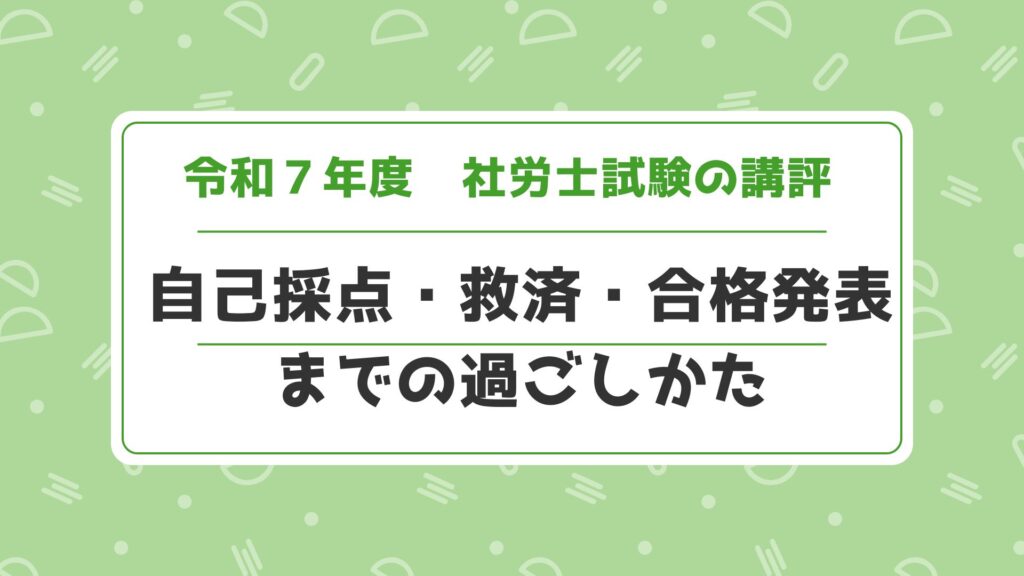はじめに
社会保険労務士試験が終わってから1週間。受験された皆さん、本当にお疲れさまでした。
僕自身、7回目の挑戦でようやく合格した身ですので、試験直後の不安や焦り、そして「救済はあるのか?」「自己採点の結果は信じていいのか?」といったモヤモヤは、誰よりもよくわかります。
本記事では、今年の試験を終えた受験生が知っておくべき「自己採点のポイント」「救済制度の仕組み」「合格発表までの正しい過ごし方」「講評の読み解き方」を、僕自身の体験談を交えながら解説します。これを読むことで、余計な不安に振り回されず、冷静に次の行動に移せるはずです。
社労士試験の自己採点 ― 合格への第一歩
試験直後、多くの受験生が一番最初に取り組むのが「自己採点」です。
しかし、ここで注意すべき点がいくつかあります。
自己採点の方法
- 各予備校(LEC、大原、TACなど)が当日に解答速報を公開します。
- マークシート控えを残していれば、自分の正答を照らし合わせて採点できます。
僕の場合、1〜3回目の受験では、全然合格レベルに達していなかったので、マークを写し忘れていたり自己採点も適当な状況でした。
4回目以降は必ず問題用紙に自分の解答を残す習慣をつけ、それを解答用紙に写すという手順を取っていました。
合格した年は、択一・選択共に どの科目が足切りの可能性があるのか
自信がある解答で何点ぐらい取れているかまで、試験時間中にある程度予測できる状態までなっていました
自己採点の注意点
- 解答速報は「暫定版」であり、後から修正が入ることがあります。
- 自己採点で合格基準に届いていても、最終的に不合格になるケースもありました。
- 逆に「ギリギリダメだ」と思っても、救済措置で合格できる可能性があります。
救済措置(科目基準点の引き下げ)とは?
社労士試験には「救済」と呼ばれる制度があります。これは、毎年の試験の難易度の偏りを調整する仕組みです。
救済の仕組み
- 本試験では、各科目ごとに「基準点(足切り)」が設定されています。
- 例:択一式なら各科目3点以上、選択式なら各科目1点以上が必要。
- しかし、極端に難しい科目がある場合、その基準点が引き下げられることがあります。
救済の考え方は、こちらの記事で説明してます
救済の過去事例
- 「労一(労働一般常識)」や「社一(社会保険一般常識)」は毎年のように救済対象になります。
- 特に「一般常識」は出題範囲が広く、運ゲーのようになりやすいため、救済が頻発しています。
僕の救済体験
僕の場合、救済で悩む年はなく、試験5回目までは、択一の点数が足りませんでした。
6回目も 選択式 国民年金 0点だったので 救済を願う状況にもなかったのです
合格発表までの過ごし方 ― 不安に潰されないために
試験から合格発表までの約3か月間、気持ちのコントロールが何よりも大事です。
やってはいけないこと
- 予備校の掲示板やSNSで「救済予想」に一喜一憂する
- 自己採点の点数を何度も見返して落ち込む
- 今回の試験結果の分析をせず「来年用の勉強」を始めてしまう
正しい過ごし方
- まずは試験の疲れを癒す → 思い切って勉強から離れる
- 家族や友人との時間を大切にする
- 気になるなら「軽い復習」だけにとどめる
7回目で合格できた前年、僕は試験後 各予備校の講評を聞き、分析に時間を使いました。
毎年のように、やみくもに学習を再開するのではなく、選択式で3点確保するための戦略を考えました
1週間ぐらいは、勉強から全く離れてリフレッシュしました。
でも、学習の習慣がなくなったしまわないように その後は 1時間ぐらいは、軽めに毎日
勉強し続けました。
そうした準備した翌年には、やるべき事はやったとうい状態で試験に望むことができました
試験講評の読み解き方
試験後、各予備校が「本試験講評」を公開します。
これは今後の学習計画を立てるうえで非常に参考になります。
講評のポイント
- 「今年の難易度はどうだったか」
- 「どの科目が合否を分けたか」
- 「救済の可能性がある科目はどこか」
例えば、今年の講評で「労一は難易度が高く、得点調整が入る可能性がある」と書かれていれば、受験生全体が苦戦したという証拠です。これは救済を期待する根拠にもなります。
僕の体験
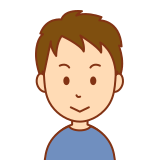
合格できなかった年は、講評を読んで「なるほど」と思いながらも結局スルーしていました。
しかし、合格した年は「自分の弱点と講評の内容」を照らし合わせ、来年に備える意識を持っていました。講評は“結果が出てからの学習”に活かす材料として使うのが良かったのかと思います
まとめ
- 自己採点はあくまで目安であり、合否を確定するものではない
- 救済制度があるからこそ、最後まで希望を捨ててはいけない
- 合格発表までの時間は「心の休養期間」として大切に使う
- 講評は将来の学習戦略に役立てる
僕は7回の挑戦を経て合格しましたが、最後の1回は、講評から選択式の対策を立てて、やることは全てやったという状況で試験は終わりました。
あとは結果を待つだけです。どうか焦らず、自分を労ってください。